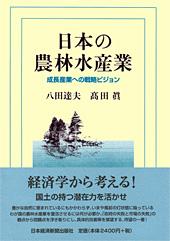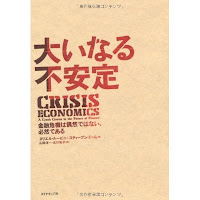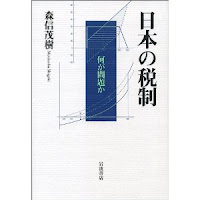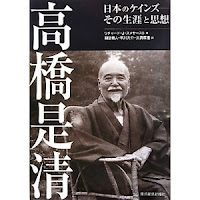(その1)では、高橋是清という人格の形成過程を明らかにすること、公職についた高橋がどのような形で独特の思想を育むに至ったのか、大恐慌時の財政金融政策をどう評価するか、そして高橋の政策が軍国主義の台頭に与えた役割、という著者が明示する4つの大きな論点のうちの前半2つの点について簡単にまとめてみた。その2では残りの2つの点のうち、大恐慌時の財政金融政策について感想を交えつつ敷衍してみよう。
3.大恐慌時の財政金融政策の評価
(1)国際環境から見た昭和恐慌の特徴
まず著者の議論に耳を傾ける前に、昭和恐慌の特徴を国際的な相違に留意しながら見ていこう(伊藤正直(2010)『なぜ金融危機はくり返すのか』旬報社、中村隆英(1993)『日本経済-その成長と構造<第3版>』東京大学出版会、長幸男(2001)『昭和恐慌-日本ファシズム前夜』岩波書店、等を参照)。
①長期停滞の後で生じた恐慌
一つ目の特徴は、昭和恐慌が1920年代の長期停滞の駄目押しのような形で生じたということである。この点は1921年から29年まで、相違はあるものの景気拡大が続いていた欧米とは対象的であり、世界的なバブルの形成と崩壊、そして世界金融危機の中で「失われた20年」に陥った我が国という、現代との比較においても奇妙な一致ともいえる(図表1)。
図表1 奇妙な一致
出所:若田部昌澄(2010)「危機の経済政策-湛山ならどう立ち向かうか」経済倶楽部講演録2010.11所収、図表3を参照しつつ作成。
少し1920年代当時の動向を跡付けてみよう。第一次大戦期の好景気(大戦景気)における1910年代の我が国は高成長(実質成長率7.3%、名目成長率27.3%)に沸き、対外債務国から対外債権国へと変貌を遂げたのだが、1920年3月の株価暴落を契機として長期停滞に陥る。そして1925年以降はデフレに突入した。デフレの持続は多くの財閥・企業を経営困難に陥らせて産業の寡占化を進め、第二次産業における熟練労働者と未熟練・若年就労者との間の賃金格差を生み出した。人員削減の中で農村から都市に流入した人々が向かったのは第三次産業、特に中小商工業であり、低賃金を前提に労働集約的なサービスを提供した。このサービスを利用したのが大企業である。以上のように、熟練労働者と未熟練・若年就労者、中小商工業と大企業といった「二重構造」を内包しつつ、デフレが続いたのである。「慢性不況」と呼ばれた1920年代には、金融危機も生じた。1927年には、十五銀行や藤田銀行、加島銀行、近江銀行が破綻し、植民地の中央銀行である台湾銀行と朝鮮銀行が事実上の破綻となった。政府・日銀は巨額の救済融資を実行したが、救済融資の返済には25年を要することになった。この結果として、1930年から31年にかけての昭和恐慌では、米国で生じたような大規模な銀行破綻と信用恐慌は生じなかった。
②震源地よりも大であった物価の下落や貿易の縮小
二つ目の特徴は、恐慌時の物価の下落率や貿易の縮小率が、危機の震源地であった欧米よりも大きかったという点である。財別に見ていくと、1929年6月から30年末にかけて生糸の価格は52%下落した。綿糸、金巾、米、大豆といった貿易財の価格も4割から5割下落した。株価は28年から先行的に下落しており、造船、鉱業及び石油、電力、化学といった重化学分野で大きかった。
③金本位制離脱と大恐慌のタイミング
三つ目の特徴は、日本が金本位制に戻ったのは世界恐慌が生じた後であったという点である。金本位制復帰の理由としては、日露戦争の際に英国から借りた四分利付英貨公債の借り換えを行うための条件であったこと、31年にできたBISの理事国となるための条件であったことが挙げられる。世界競争から脱落者になるのを防ぎ、国際標準に適合する道として、金本位制の復帰が位置づけられ、これができなければ日本は世界の三等国になるというのが当時の政府の判断であった。しかし、金本位制への復帰は、ウォール街の株価暴落が生じた後となった。そして、恐慌下で膨大な量の正貨(金)が流出する。正貨流出額は30年~31年にかけて7億8700万円、我が国の正貨保有高は金輸出解禁時点の13億4400万円から31年12月末には5億5700万円へと激減したのである。
④急速な恐慌からの回復
四つ目の特徴は、恐慌からの回復が極めて急速であったということである。日本は31年12月に金本位制を停止し、32年に高橋財政がスタートしてから、工業製品を中心にして恐慌からの回復が極めて短期間で生じた。米国や欧州は、38年~40年の時点でようやく29年の水準を回復したのに対して、日本は34年には既に29年の水準を回復した。具体的には、1920年代の「失われた10年」においてマイルドなデフレ、昭和恐慌時には10%というデフレを経験した日本経済であったが、高橋財政により2%程度のマイルドなインフレーションと7%程度の実質成長を可能とするまで回復したのである。
だが、この回復は農業とその他産業ではズレがあったことも指摘せねばならないだろう。例えば米の生産や価格が回復していくのは1935年のことであり、生糸が29年の水準を回復したのはずっと後のことであった。先程停滞には「二重構造」を内包したと書いたが、停滞からの回復も又ばらつきが生じていたのである。
(2)日本のケインズ
①高橋の経済政策における4つの疑問
長々と昭和恐慌前後の特徴を概説した理由は、以上の話をあらかじめ頭に入れておくことで、著者の議論を読んだ方がより面白いのではないかと感じたためである。
さて本書で高橋の経済政策についての記述がなされる箇所は、「日本のケインズ」と銘打たれた第12章である。高橋が大蔵大臣に就任したとき、物価は急落、失業は増加、農家は農産物価格暴落により打撃をうけ、鉱工業生産は停滞して工場は休業ないし稼働率が低下した状態にあり、新規設備投資はほとんど行われていなかった。こうした問題に対処すべく、半年あまりで高橋は前任者の緊縮政策を劇的に転換させ、非伝統的な財政金融政策の導入により景気刺激をはかり、日本経済を回復へと導いたのである。
金融政策では、日本を金本位制から離脱させて紙幣の金との交換可能性を絶ち、ドルとポンドに対して円を切り下げ、公定歩合を引き下げて金利の低下を促し、日本銀行券の発行限度額を引き上げる法律を導入した。通貨切り下げによって、貿易縮小が生じた世界とは異なり日本の輸出は好調を維持した。
さらに高橋は、需要刺激のために財政支出を拡大させることで景気変動を平準化させるという財政政策を行った。高橋は歳入と歳出の差額を増税で埋めるのではなく、低利の国債を日銀に直接売却するという「引き受け」により埋め合わせた。これにより、政府支出はマネーの増加を通じて有効需要を拡大させ、輸出の増加と相まって生産と雇用を刺激した。
時系列で高橋の行った経済政策をみていくと、金輸出再禁止(金本位制からの再離脱)が1931年12月13日、日銀による赤字国債の引受けが行われたのが1932年11月~1935年末、拡張的財政政策の実行は1932年夏に成立した1932年度補正予算から1936年度予算までの期間である。財政政策と金融政策の両輪を働かせたのが高橋の経済政策の特徴だが、金輸出再禁止の実行から拡張的財政・金融政策の実行の間にはラグがある。後でみるように、このラグの時期に行われた政策、およびその背後で政策当局がどう関わったのかという点が興味深く感じるところだ。
さて、著者は、第12章の議論を進めるにあたって、いくつかの疑問を提示している。ひとつは、金本位制離脱による円切り下げは「近隣窮乏化」政策に結びつくのではないかという点だ。そして二点目は、国債引き受けを伴う政府支出の拡大が、大蔵官僚や中央銀行員に市場の制約を無視して通貨供給量を拡大させる権限を与えたという意味で危険ではなかったかという疑問である。三点目は、高橋が行った時局匡救事業と軍事費を中心とする財政支出は、軍国主義の台頭や我が国が引き起こした戦争に向けて決定的な役割を果たしたのではないかという疑問である。最後の疑問は、なぜ高橋は時局匡救事業を1934年に終了させてしまったのかという点である。
これらに答える形で議論は進んでいくが、(1)でふれた昭和恐慌突入の過程と、井上・高橋の論争といった点の記述も臨場感あふれる筆致で興味深い。本書の記述を読んで自分が興味深く感じた点も合わせてふれながら見ていこう。
②深井英五の役割
自分が興味深く感じた点の第一は、高橋が大蔵大臣に就任し、金輸出再禁止が実行された時期(1931年12月)の前後における深井英五の役割である。
深井は当時日銀副総裁であり、高橋が日露戦争の戦費調達のためロンドンに滞在した時(1904年~1905年)からの側近である。深井は、井上の後に大蔵大臣の指名を受けることが確実視されていた高橋のもとを訪れて、金本位制離脱と金輸出を速やかに禁止すること、早急に日本国内で通貨を金に兌換することを禁止する勅令を公布する準備を進めるべきことを進言した。高橋は金本位制離脱と金輸出禁止には賛成するものの、金兌換停止には懸念を表明する。それは、高橋でさえも現下の危機からの脱却が可能となった暁には金本位制に復帰するものだと考えており、円の価値を安定化させるアンカーを持たずに円相場を変動させることへの危惧があったためである。通貨の番人たる深井が通貨のアンカーとしての金からの離脱を支持し、逆に放漫財政との批判もあった高橋がこれに懸念を表明するという図式はいささか奇妙なものだ。
ただし深井と高橋は、日本が管理通貨制を採用するのであれば、深井が提示した「生産性と通貨供給量を調和させるような金融政策を遂行することが必要」という点では合意していた。高橋の後を継いだ大蔵大臣らは、この金言を無視するようになり、そして1937年の初めに深井は日銀総裁の職を辞することになったわけだが、この点は著者の言うとおり日本にとって不幸な事態といえるだろう。
③円切り下げに関する当時の論争
高橋と深井が考えた政策は、輸出促進のために円を切り下げ、金本位制の制約を外すことで通貨供給が行えるようにして流動性を供給するというものであった。
著者は金本位制離脱と円切り下げ政策に対する当時のマスコミの反応として、『東京日日新聞』や『エコノミスト』、『東洋経済新報』の論調を取り上げる。
『東京日日新聞』や『エコノミスト』の論調は、金本位制からの離脱は不可避であり、卸売物価や消費者物価の回復が予想されるものの、インフレを防止するためにこの拡張政策を注意深く監視すべきだというものであった。そしてジャーナリストの中では、『東洋経済新報』の石橋湛山とその仲間達がデフレの有害な影響を認識していた。『エコノミスト』では、経済学者は金本位制からの離脱には一致して反対していたが、同誌は「経済学者は通常の学問的立場から」高橋を批判しており、彼の政策が経済に対して有害であるという理由からではなく、彼の政策が正統的な経済理論に反するという理由から反対している、と述べている。ケインズの『貨幣改革論』を現実の政策に活かそうとしたのは石橋らのグループのみであった。この一節を読んで、現代における「正統派」の議論にも同様の側面が垣間見えると自分は思う。
そして作者の論争の紹介は、32年1月21日の高橋・井上による「OK牧場の決闘」の記述で最高潮を迎える。「OK牧場の決闘」が行われたのは、高橋が所属する政友会が民生党を抑えて総選挙にて勝利する1ヶ月前のことである。
高橋と井上の議論は、現代における通貨切り下げ競争と金融緩和策の評価に関する議論を考えると意味深い内容である。彼等の主張を紹介しよう。
高橋はまず日本における恐慌の原因は、浜口・井上の「超緊縮予算」であり、世界的に採用されたデフレ的な政策により引き起こされた大恐慌は日本にも影響を与えたが、日本の経済的苦境は主に民生党の政策によるところが大だと表明する。前政権の政策は、金融を閉塞状況に陥らせ、産業は衰退し、日本経済を不況のどん底に落としめた。金輸出再禁止は、このような状況を打開する第一歩であるというのが高橋の主張である。
一方で井上は反論する。高橋は誤っている。まず、日本における恐慌は世界の他の地域に比べて軽微なものに留まっているというのが世界の財界人の一致した見解であると論じる。そして為替相場の切り下げにより輸出を拡大させるという高橋の構想を批判する。井上は円の切り下げが日本経済の回復をもたらすことはないと述べる。この理由として、円を切り下げても米国向けの生糸輸出が利益を受けることはなく、他国は日本からの輸入を抑制するために、通貨切り下げや関税引上げといった報復措置を取ることが予想される。そしてマネーの増加はインフレにつながり、国民生活に打撃を与える。そして高橋の構想が日本のためになるとしても、これは他国の犠牲において日本の国益を推し進めるものであって、国際倫理に反するというものだ。
高橋と井上の議論は、鋭く対立する二つの政策的立場を表明したものであった。井上が提唱した政策は、国際金融市場の秩序に則るというものだ。国際的な枠組みが崩壊しつつあるのならば、日本を優先することが高橋の考えであった。そして、この二つの立場は日本の立ち居地についての齟齬からも生じる。つまり、井上の議論は日本が実際よりも金融大国であるという自負から生じたのかもしれず、それは国際金融市場の大御所と井上のつながりによるものなのかもしれない。一方で高橋は経済的にも金融的にも、日本は小さな存在であることを自覚していた。この点、日露戦争時の外債発行における経験、つまり英米と比べ日本の力が弱小であったことを自覚していた点も影響していたのかもしれない。
ややわき道にそれるが、日本は小さな存在であるという高橋の認識は石橋湛山の「小日本主義」にも通暁するのではないか。対極としての「大日本主義」は軍備拡張と植民地拡大へと繋がるが、その中で台頭したのは軍部であったのは言うまでもない。一方で小日本主義は、軍備拡張と植民地拡大を否定し、自由主義と自国の経済的安定のための資源の重点配分を旨とした。この点、高橋と石橋の思想、更にはケインズをはじめとする世界の一級の経済学者の思想との共通点があったといえるのではないだろうか。だからこそ高橋はケインズに先駆けて拡張的財政・金融政策を実行に移せたのであろうし、石橋は経済学のエッセンスを体得することができ、現実に即した柔軟な思考を持ちえたのではないか、そんな風に感じた次第だ。
④金融面での準備的政策の実行
先程書いたとおりだが、自分は昭和恐慌下における一連の経済政策の中で、国債引き受け・財政拡張に至る前段階としての金融緩和策が(財政・金融政策の大々的な実行とあわせ)重要ではなかったかと考えている。
ある政策が望ましいと分かっていても即座に実行に移すためには「政策のインフラ」と呼ぶべきものが整備されていることが必要だ。卑近な例かもしれないが、最近の事例で考えれば、定額給付金や子供手当てといった家計への直接支給を行う際に、あらかじめ納税者番号制度といった政策インフラが整備されていれば実行はより容易となったはずだ。また給付付き税額控除といった政策も容易に行うことが可能になる。国債引き受けを伴う金融緩和と財政政策の実行を強力に進める前段階においても、それを可能にする準備的政策が着々と実行され、それが本来の政策の効力を増すことに影響したのではないかということだ。
著者は、金融面で二つの施策を用意していたと述べる。一つはマネーサプライを大々的に増加させることを可能にするような制度的枠組みである。具体的には、1932年6月の兌換銀行券条例中改正法律、日本銀行納付金法、日本銀行参与会法の制定である。重要なのは兌換銀行券条例の改正だが、これにより日銀の保証準備発行限度1億2000万円が10億円まで増額された。そして制限外発行の要件も緩和された。
もう一つは、低金利政策の実施である。公定歩合は高橋就任時には5.84%だったが、33年には3.65%に引き下げられ、蔵相在任中にはこの水準が維持された。低金利政策の実行は、低利での国債発行を容易にするという側面と、企業が事業拡大を行う際の資金調達を容易にするという側面もあった。
本書では登場しないが、国債引き受けを容易にするという視点で言えば、伊藤(2009)でも指摘があるように、当時高橋は国債優遇措置のための政策を行ったということも指摘しておくべきだろう。つまり1932年4月の国債担保貸出に対する高率適用の緩和であり、32年7月の「国債ノ価額計算ニ関スル法律」の公布である。前者は融通期間30日以内の国債担保貸出について従来適用されていた金利を適用しないと決めたことであり、後者は商法の規定に関わらず国債については取得当時の時価を越えない範囲で大蔵大臣の交付する標準発行価格を帳簿価格とすることを認めたというものである。この制度により、国債の市場価格が下がっても評価損を計上する必要がなくなったというわけだ。国債価格が政府により管理されるため、金融機関の国債保有は安全有利な形となったのである。
さて、大規模な財政・金融政策を行う前段階としての制度改正は、当時の日銀が「日銀による国債引き受け」に(後世の整理とは異なり)前向きであったのではないかとの考えをよぎらせる。確かに深井英五は、日銀による国債引き受けを後に「最大の失敗」であったと反省したのは有名な話であり、『日本銀行百年史』でも「本行引受による国債発行の危険性については、本行もある程度意識していたことは明らかであるが、結局高橋蔵相の強力な要請に押し切られ、『一時の便法』としてこれを容認したものと思われる」と述べて高橋のリーダーシップに原因を求めている。だが、1932年6月の兌換銀行券条例中改正法律、日本銀行納付金法、日本銀行参与会法の制定や、先に見た深井の高橋に対する金輸出再禁止の進言、そして深井が「生産力と通貨との均衡を主たる目標として通貨の運営を按配すべし」とし、金融や財界の閉塞を打開するには金本位制からの離脱が必要であると考えていたことを勘案すれば、マネタリーベースの円滑な拡張のために対民間信用のみならず対政府信用を活用するという可能性を現実的な路線として判断したとする伊藤(2009)の議論の方が説得的と感じられるのである。
⑤高橋が直面した政治・経済状況
そして高橋の経済政策を考えるにあたり考慮すべき点は、昭和恐慌後の政治・経済状況についてである。著者が述べるように、昭和恐慌は政治及び経済の両面で日本に大きな傷を残した。悪循環に陥った経済の中で、世界各国は保護主義的な経済的自立を選択していく。米国は悪名高いスムート・ホーレイ関税法を成立させて関税を史上最高の水準まで引き上げた。英国は連邦諸国に対して特恵的な扱いを認めた。その他の諸国も英米に対抗して報復的に関税を引き上げるようになる。崩壊しつつある世界経済の枠組みを目のあたりにした高橋が、日本のみがその枠組みに忠実であることに何の利点も無いと考えるのは自然なことだろう。このような局面の中で政党に基盤を置く井上や、協調外交の立役者であった幣原、犬養、そして高橋自身も、政治的集団の中で徐々に信頼を失っていく。彼らに反対する勢力は、外交的・軍事的な自主性と、政党政治の廃止を提唱することになる。
彼らに反対する勢力、つまり「自立日本の追求」を掲げる人々の中で最も強力な一派は軍部であった。陸軍は1931年9月に中国東北部に進出し、大衆はこれを喝采で迎えた。1920年代に民主主義をはぐくんだ大衆社会は、30年代には国家主義の潜行、米国の排外主義に対する敵意、中国の民族主義的抵抗に対する怒り、恐慌下における日本人の苦痛、矛盾、といった内外環境に関する様々な要素が混在しつつ、兵隊さん、分かりやすい答えを出してくれる人、弱腰な民主的妥協ではなく直接的行動と専制政治を提唱する人、つまり軍部への熱狂的な支持を集める土壌が生じた。そして政友会の主要人物の中でさえも、森格のように自らのよってたつ政党政治を反対することに加担する人物も出てくるようになった。
1931年から36年にかけて、軍部の様々な勢力が、海外侵略、国内クーデター、暗殺といた暴挙に出て、日本の政治と外交政策を変質させてしまう。これは協調を提唱した人々を殺すか沈黙させることに繋がった。1931年12月に高橋は5度目の大蔵大臣に就任し、1932年5月15日の犬養首相暗殺後の5月26日に6度目の大蔵大臣に就任することになる。 高橋が経済政策を行っていたのは、以上のような政党政治に対する軍部の圧力、その背景にあった閉塞感といった状況下であった。そして犬養内閣の後継内閣は政党内閣ではなく退役海軍大将の斎藤実を首班とする内閣であった。斎藤内閣の成立に際しては、与党政友会と軍部との関係や政友会の強硬な外交政策の危惧もあったため、政党内閣ではなかったことも重要な特徴だ。(その3)でふれることになる軍部の圧力に対する高橋の抵抗は、命の危険と隣あわせの中で繰り広げられたことも留意すべきだろう。
⑥財政・金融政策の実行
6度目の大蔵大臣に就任した高橋は、1932年6月3日と8月25日の二回にわたって議会にて財政に関する重要な演説を行った。高橋が表明したのは、公共事業の拡大や軍事的費用の支出を含む政府支出の大幅拡大、不況により減少した税収と拡大する財政支出の差を埋めるために国債を発行すること、大蔵省はこの国債を日銀に引き受けさせ、日銀は適切な頃合いを見計らって引き受けた国債を市中で売却すること、既にみた銀行券の保証発行限度額の大幅拡大、金利の引下げの促進、地方銀行への融資拡大を通じた地方金融の増強といった政策であった。
そして高橋は1936年にかけてこれらの政策を実行していく。筆者の整理に従いながらみていくと、1931年度の中央政府の歳出は15億円であったが、32年度の歳出は20億円と3分の1増加した。税収は低迷していたため、歳出と歳入の差額は国債発行で穴埋めされるが、国債発行額は31年度の3000万円から32年度に7億円と大幅に拡大する。1935年度までの歳出は20億円~23億円の水準で推移し、国債発行額は6億円から9億円のレンジで推移した。日本銀行はこれらの国債を引き受けたが、35年末までに引き受けた国債の9割を市中で売却したことも注意すべきだろう。つまり、日銀は国債を引き受けることで増加した流動性を一定の期間を経てほぼ吸収していたのである。深井が言う「一石三鳥」の妙手というわけだ。そしてこの間の消費者物価の上昇率は年率3%未満と低位に抑えられた。
高橋が行った政策は、軍部、文民官僚、恐慌対策(時局匡救事業)向けの支出を増加させた。軍部の予算は1931年度から1933年度にかけて2倍以上に拡大し、35年度までに10億円を超え、政府予算の半分弱を占めるようになった。軍部以外の省庁による支出は1931年度から33年度にかけて16%増加し、34年度、35年度とわずかに減少した。中央政府は1932年度から34年度にかけて5億4400万円を時局匡救事業として支出したが、その後全ての企業が廃止された。1932年度から34年度にかけての政府(中央及び地方)の投資は17億円に相当し、恐慌対策としてかなりの効果を上げたが、それでも軍部が受け取った金額の3分の2には届かなかった。
マクロ経済学的な見地からすれば、高橋の政策の効果はめざましい。1931年から36年にかけて国民所得は6割の増加、消費者物価の上昇は18%であった。つまり、名目で見ても実質で見ても国民所得は急激な伸びをみせたのである。井上財政期の状況(名目所得2割減少、実質所得も停滞)と比較すればそれは明らかだろう。そして就業者数が増加し、36年には完全雇用の状態に日本は復帰する。個人所得も回復していき、タイムラグを経て経済の最低層であった農業労働者の実質賃金も35年から39年の間に増加に転じた。日本は米国よりも5年も前に世界恐慌から脱却し、ドイツを除くどの先進国よりも劇的な復活を果たしたのである。
⑦高橋は「近隣窮乏化」政策を進めたのか?
さて、著者は最後に当初指摘した4つの質問のうち、前半二つの質問に答えている。高橋は「近隣窮乏化」政策を進めたのか?著者の答えはイエスだ。
しかし、著者が注意深く指摘するように、米英をはじめとする先進国経済が自国を第一に考え、国際協調と呼ばれるものが各国の財政指導者にデフレ的な政策を要求する状況で、「日本の」経済を恐慌から脱却させるためには他に選択肢は無かったとも言えよう。この状況は自分にとってはまさに現在と通じると感じる。現代においても世界的な金融緩和競争の様相を呈する中で、国際協調といった文脈では財政支出の切り詰めといったデフレ的な政策が志向される状況がある。昨今急激な形で進んだ円高もこの二つの「差」を政策当局が見抜くことができず、適切な政策が打てていないことに原因があるのではないか。そしてまさに大恐慌からの脱出は、各国が金本位制のくびきから逃れ、自ら金融緩和を積極的に行うという形を通じてなされたという点も考慮すべきだろう。
⑧高橋の政策がその後の放漫財政の道を開いたのか?
著者は二番目の問い、つまり高橋が1932年に財政支出の拡大を行ったことで、放漫財政に日本は陥ったのか?という点についてはどう答えているか。この点についての著者の答えは同意するところだが、つまりインフレはいつどんな状況でも許容できず、国民所得の停滞とともにデフレが進行しているような状態においても許容できないのならば、高橋の政策は放漫財政であったというものだ。しかし、財政安定は国民所得の安定的増加よりも上位の目的なのだろうか。そうではないだろう。
高橋の政策が放漫財政に繋がったという意見に賛意を持つ人々はこういうかもしれない。曰く、戦時インフレの端緒となったのが高橋の財政政策によるものであり、また国債の日銀引き受けという制度によるものだと。しかし著者が言うように、高橋は常々、財政拡大と政府支出の増加は急場しのぎの一時的政策で、日本が恐慌から脱出した際にはやめるべきものだと述べていたことを忘れている。そして次で見るように、様々な制約の中で高橋が断固として歳出拡張を求める軍部と戦っていたこと、その果てに暗殺されたことも考慮すべきだろう。さらに、高橋死後の急激なインフレが生じたのは、戦費調達のために著しく過剰な形での国債の日銀引き受けが行われ、それが公開市場で売却(つまり吸収)できなかったことが、貨幣の増発に繋がったことが理由である。高橋が編み出した政策の運用が不味かったことで政策を編み出した張本人の責任とするのは後の人間の傲慢でもあり、お門違いの批判だろう。
現代においても高橋の政策、特に国債の日銀引き受けに対する批判は根強い。勿論、非伝統的な政策をやらずに済むのであればそれに越したことは無いが、必要なタイミングであるにも関わらず運用の危険を殊更重視するのは誤りではないか。後世の人間の唯一の利点は、先人の勇気ある決断と行動を、その当初の状況だけではなく帰結に至る過程まで捉えることが可能だという点だろう。運用に問題があるのならば、単なる批判ではなく、運用をうまく行うための工夫こそ、後世の人間が考え、行動すべきことなのではないか。本書を読んで改めて感じた次第である。